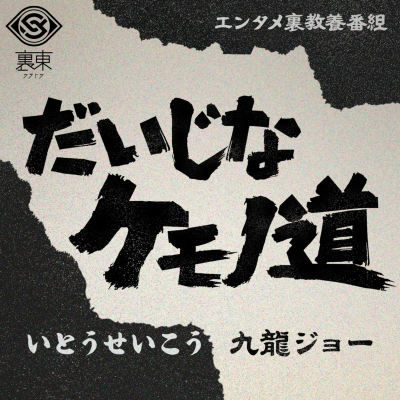
だいじなケモノ道
Podcast von ウラトウ
■「だいじなケモノ道」 エンタメ道の裏側=ケモノ道を語り継いでいく、エンタメ裏教養番組『だいじなケモノ道』。いとうせいこうと九龍ジョーの二人がテレビ、舞台、音楽ライブなどのエンタメを支える裏方ゲストを迎え、時代を作った演出や革命を起こした技術など、いまだ明るみになっていない類まれなる仕事に光を当てていく。 毎週木曜日 最新話配信 出演:いとうせいこう、九龍ジョー 作家:竹村武司 ディレクター:中内竜也 プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
Nimm diesen Podcast mit
Alle Folgen
26 Folgen今回は特別編として『BRUTUS』No.994紙上にも掲載された鼎談の模様をお送りします。お相手はヒップホップユニット"Dos Monos"として活動しながら、ポッドキャスト番組『奇奇怪怪』を手がけるTaiTanさん。『だいじなケモノ道』のヘビーリスナーであるという彼の指名で実現した、『奇奇怪怪』の書籍第2弾発売を記念する現代の“おしゃべり”談議です。情報過多が進み、ランキングの機能しないこれからの時代のカルチャーにおいて、最も重要な役割を担う「編集」。それを"一つ一つ細かくピンセットで摘むような手つきできちんとさばいている"『奇奇怪怪』と、これまで"エンタメの裏方"についてマニアックに掘り下げてきた『だいじなケモノ道』という、共通する視座をもつ両番組の鼎談ということで、話題は「言語」の起源や「しゃべり」の情報性、「タイパ時代の〇〇」のような流行のスローガンへ安易に回収されない、ポッドキャストそのものの役割にまで深まっていき.... ※本記事は『BRUTUS』のWebページでも公開されております。ぜひご一読ください! https://brutus.jp/podcast_discussion/ 写真:Jun Nakagawa ■番組概要 毎週木曜日 最新話配信 出演:いとうせいこう、九龍ジョー 作家:竹村武司 ディレクター:中内竜也 プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀
テレビというメディアの重大な構成要素である「音声」に関する考察を深めていった結果、話題は"どうしたら発言が使われるか"、ひいては"どうしたら売れるのか"という演者側の技術論まで発展。清水さんによると、実は撮影現場でタレントを"一番よく見ている"のは「音声さん」ではないかということで、特に"ながら視聴"されるようになったテレビで売れていきたい若手が意識するべきポイントを紹介してくださったことをきっかけに、「芸人講座」のような展開に。シーズン1最終回にして、いとうせいこうが当番組で「テレビの技術論」をやりたかった理由の核心へ触れます。エンタメの話題は尽きないなか、シーズン2の構想も飛び出すが.... ※シーズン1は今回で一旦区切りとなります。またぜひ、「ケモノ道でお会いしましょう」! ■番組概要 毎週木曜日 最新話配信 出演:いとうせいこう、九龍ジョー 作家:竹村武司 ディレクター:中内竜也 プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀 ※番組内の用語注釈 ・00:47【クイズプレゼンバラエティQさま!!】 2004年からテレビ朝日系列で放送されている、さまぁ〜ず司会のクイズバラエティ番組。 ・01:30【ガンマイク】 指向性が鋭く、少し離れた場所でもマイクが向いている方向の音をしっかり拾うことができる音声収録機材。 ・03:19【Qさま!!いきなりチキンレース】 番組初期に放送されていたロケコーナー。芸人が高さ10mのジャンプ台から、プールに飛び込むまでどれくらい時間が掛かるかを競う企画。 ・04:27【主導権を握る人】 前回#23の15:53〜19:40のトークを参照 ・07:03【ブーム】 ポールの先端にガンマイクを取り付けて音声収録を行う方法。 ・15:32【オフコメ】 オフコメントのこと。アナウンサーやレポーターが画面に登場しないで、声だけが聞こえる状態。
テレビ朝日の技術職として、数々の有名バラエティ番組、「朝まで生テレビ」「報道ステーション」などの報道番組に携わってこられた清水さんをお招きし、テレビというメディアを"音声"の面から支えてきた裏方について掘り下げていきます。実際にテレビに出演する側である二人も、"何十年も一緒に仕事をしてきた"身近な存在でありながら「音声さん」の実態をほとんど分かっていなかったとのこと。番組や出演者のキャラクターを生かしながら、"プロとして恥ずかしいことにならないようにする"職人仕事の繊細さに二人は終始驚かされ、話は"どうしたら音声をオンエアで使ってもらえるか"というような出演者側の技術論にまで発展していきます。さらに「だいじなケモノ道」の配信をご覧になった清水さんによれば、当番組のマイクのつけ方も最適ではないようで.... ■番組概要 毎週木曜日 最新話配信 出演:いとうせいこう、九龍ジョー 作家:竹村武司 ディレクター:中内竜也 プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀 ※番組内の用語注釈 ・06:43【ミキサー】 ミキサーという機材を使い、現場で出演者の声、VTRの音など、音量のレベルを調整する作業。 ・06:47【サブ】 副調整室。テレビ、ラジオなどの放送局でスタジオに設けられた音声や映像などを調整するための操作室をいう。略語で「サブ」と呼ばれる。 ・06:49【福元昭彦】 テレビ朝日制作技術センターに所属。「虎ノ門」「いきなり!黄金伝説」などのスイッチャーを担当。当番組にもゲスト出演した。 ・07:03【ブーム】 ポールの先端にガンマイクを取り付けて音声収録を行う方法 ・07:16【無線の技術】 ワイヤレスマイクを使用する際、周波数を設定し、空中を飛び交う電波を利用するので無線の知識が必要となる。 ・13:26【サオ】 ブームのポール部分のこと。 ・19:30【虎の門】 2001年から2008年までテレビ朝日で生放送されていた深夜のバラエテイ番組。いとうせいこうが定期的にMCを務め、「うんちく王決定戦」や「しりとり竜王戦」などの企画が人気を博した。 ・24:52【ゲイン】 ミキサーに入力される音の信号の大きさを調整するもの。
今回は"九龍ジョーがいとうせいこうにどうしても話を聞きたかった"人物、景山民夫について。晩年の不穏な状況もあり今では言及されることが少なくなったものの、『シャボン玉ホリデー』『11PM』『クイズダービー』といった数々の名番組を手掛け、作家としてテレビの歴史を作ってきた人物である景山の知られざる足跡を二人で辿ります。ジャンル横断的に各所へ首を突っ込み、若い才能を発掘しながら次世代へ多大な影響を与えてきた景山の功績は世間の評価以上に大きく、"自身もフックアップされた一人"であると言ういとうによれば、彼は"日本カルチャー界のものすごい台風の目"であり、"「テレビ」というメディアの別の可能性を考えるうえで準拠すべき点"でさえあったとのこと。テレビがかつての勢いを失い、昭和の偉人たちも次々とこの世を去っていくなか、もし景山のような人物がいたとしたら「日本のカルチャー」はどんな姿になっていたのか.... ■番組概要 毎週木曜日 最新話配信 出演:いとうせいこう、九龍ジョー 作家:竹村武司 ディレクター:中内竜也 プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀 ※番組内の用語注釈 ・00:55【景山民夫】 1947年-1998年 放送作家として「11PM」「クイズダービー」「タモリ倶楽部」など数多くの番組を担当。その後、文筆業に進出し、小説家として1988年「遠い海から来たCOO」で直木賞を受賞。 ・01:15【宮永正隆】 音楽評論家、プロデューサー。いとうせいこうの早稲田大学時代の同級生。大学卒業後、集英社に入社し「ちびまる子ちゃん」の編集を担当した。 ・01:50【ノーライフキング】 1988年出版された、いとうせいこうによる一作目の小説作品。 ・02:01【虎口からの脱出】 1986年出版された、景山民夫による満州事変をモチーフにした冒険活劇小説。 ・04:09【桑原茂一】 プロデュースカンパニー「株式会社クラブキング」代表取締役。1975年、小林克也、伊武雅刀とユニット「スネークマンショー」を開始。1982年原宿に開店した伝説のクラブ「ピテカントロプス・エレクトス」の代表を務める。他にも「コム・デ・ギャルソン」のショーの選曲を担当するなど活動は多岐に渡る。 ・04:16【宮沢章夫】 1956-2022年 劇作家、演出家、作家。1985年、シティボーイズ、竹中直人、いとうせいこうらとユニット「ラジカル・ガジベリベンバ・システム」を結成し活動。その後、劇団「遊園地再生事業団」を主宰し、1992年に発表した「ヒネミ」で岸田國士戯曲賞を受賞。2016年から早稲田大学文学学術院教授を務めた。 ・04:37【シティボーイズ】 大竹まこと、きたろう、斉木しげるによるコントユニット。1979年劇団「表現劇場」のメンバーだった3人で結成。 ・04:40【竹中直人】 俳優、映画監督。宮沢章夫と多摩美術大学の同級生。竹中がシティボーイズに宮沢を紹介したことで、ラジカルの活動につながっていった。 ・04:42【中村ゆうじ】 俳優、タレント。1980年代後半にシティボーイズ、いとうせいこうらと演劇ユニット「ラジカル・ガジベリベンバ・システム」を結成。 ・04:47【ピテカントロプス・エレクトス】 1982年原宿に開店した伝説のクラブ。坂本龍一やデヴィッド・バーンなどのアーティストがライブを行った。ファッション、音楽、芸能関係者が集まり最先端の文化交流の場だった。 ・07:13【青島幸男】 1932-2006年 作家、作詞家、放送作家、タレントなど様々な分野で活躍。1995年から1999年まで東京都知事を務めた。 ・07:42【高田文夫】 1948年生まれ 放送作家、タレント。放送作家として「オレたちひょうきん族」「夜のヒットスタジオ」「ビートたけしのオールナイトニッポン」など数多くの番組を担当。その後、落語家「立川藤志楼」として真打に昇進。ラジオパーソナリティとしても活躍。 ・09:11【遠い海から来たQOO】 1988年出版された、景山民夫による海洋冒険小説で直木賞受賞作品。 ・10:27【藤原ヒロシ】 プロデユーサー、ミュージシャン。1983年クラブDJとして活動開始。1985年高木完とヒップホップグループ「タイニー・パンクス」を結成。デビューアルバム「建設的」にいとうせいこうが参加した。 ・15:45【ロビー・ロバートソン】 10代半ばで後にボブ・ディランのバックバンドとなるホークスに加入。ホークスは1968年ザ・バンドと改名し、1994年ロックの殿堂入りした。 ザ・バンド解散後は映画音楽を手がけマーティン・スコセッシ監督作品を数多く担当した。 ・16:54【小黒一三】 1950年生まれ 編集者。マガジンハウスで雑誌「ブルータス」などの編集を担当。その後、独立し雑誌「ソトコト」を創刊した。景山民夫の武蔵中学・高校時代の後輩で、影山にエッセイを依頼し作家デビューのきっかけを作った。 ・18:03【大根仁】 1968年生まれ 演出家、映画監督。バラエティ番組のディレクターからキャリアをスタートし、映画「モテキ」ドラマ「エルピス-希望、あるいは災い-」などを監督。ポップカルチャーに造詣が深い。
今回は「ビッグ3」の一角とも言われる巨人・タモリについて。デビューから半世紀にも及ぶこれまでの彼の歴史を、テレビや芸能界自体の変遷と重ね合わせながら、自身もその後継者の一人と目されてきた立場であるいとうせいこうと九龍ジョーが改めて考察していきます。ある意味で"釈迦"の生涯にさえ準えられる極端な転身により、"夜"のアングラ芸人から一躍"昼"の顔になったタモリ。彼は「笑っていいとも」でどんな"笑い"をし、どう振る舞ってきたか。そして「いいとも」以後の令和の時代に、もし彼のような役割を担える人物がいるとしたら、それは誰か。最後にいとうはこれから「テレビ的なもの」が残っていく可能性として、"朝"という時間帯を挙げ.... ■番組概要 毎週木曜日 最新話配信 出演:いとうせいこう、九龍ジョー 作家:竹村武司 ディレクター:中内竜也 プロデューサー:井上陽介(テレビ東京コミュニケーションズ)、柳橋弘紀 ※番組内の用語注釈 ・02:37【赤塚不二夫】 1935-2008年 漫画家。代表作「天才バカボン」「おそ松くん」「ひみつのアッコちゃん」など。タモリはデビュー前、1975年ごろ新宿の酒場などで宴会芸を披露していたところを赤塚にスカウトされ、赤塚の自宅に居候していた。 ・02:35【山下洋輔】 1942年生まれ ジャズピアニスト。1972年、山下がコンサート後打ち上げしていた、福岡のホテルの部屋にタモリが乱入し、芸を披露したことから交流が始まる。この出会いが、後にタモリが芸能界デビューするきっかけとなった。 ・03:25【タモリライフ研究会】 いとうせいこうが早稲田大学在学中に所属していたサークル。 ・03:47【空飛ぶモンティ・パイソン】 イギリスの伝説的なコメディグループ、モンティパイソンによるテレビ番組。日本では1976年から東京12チャンネル(現テレビ東京)で吹替版が放送された。その際、番組のおまけコーナーにタモリが出演、実質的なデビューだと言われている。 ・04:06【藤村有弘】 1934-1982年 「インチキ外国語」の芸を得意とした喜劇人。 ・04:55【宮永正隆】 音楽評論家、プロデューサー。いとうせいこうの早稲田大学時代の同級生。大学卒業後、集英社に入社し「ちびまる子ちゃん」の編集を担当した。 ・05:26【青島幸男】 1932-2006年 作家、作詞家、放送作家、タレントなど様々な分野で活躍。1995年から1999年まで東京都知事を務めた。 ・05:35【大橋巨泉】 1934-2016年 音楽評論家、放送作家としてキャリアをスタート。1960〜80年代、司会者として「11PM」「クイズダービー」など多くの人気番組に携わった。 ・05:38【前田武彦】 1929年-2011年 タレント、司会者、放送作家。放送作家として「シャボン玉ホリデー」を立ち上げ1960年代ごろからタレント活動が本業となり「夜のヒットスタジオ」の司会を務めた。 ・07:01【景山民夫】 1947年-1998年 放送作家として「11PM」「クイズダービー」 「タモリ倶楽部」など数多くの番組を担当。その後、文筆業に進出し、 小説家として1988年「遠い海から来たCOO」で直木賞を受賞。 ・07:25【ばらえてい テレビファソラシド】 NHK総合テレビで1979年から1982年まで放送、タモリがレギュラー出演していたバラエティ番組。タレントだけでなく学者や教授がゲスト出演する知的エンタテインメント番組として評判になった。 ・07:42【今夜は最高!】 日本テレビで1981年から1989年まで放送されていた、タモリが司会のトーク・コントバラエティ番組。 ・07:45【高平哲郎】 1947年生まれ 放送作家、編集者、評論家。タモリとデビュー前から交流が深く、放送作家として「今夜は最高!」「笑っていいとも!」などを担当。 ・08:57【向田邦子賞】 優れたテレビドラマの脚本作家に与えられる賞。バカリズムは「架空OL日記」で2017年度受賞。 ・10:32【スター千一夜】 フジテレビ系列で、フジテレビの開局日である1959年3月1日から 1981年9月25日まで約22年半放送されていたトーク番組。 ・11:37【宇多丸】 1965年生まれ ラッパー、ラジオDJ、ライターで。ヒップホップグループ「ライムスター」のMC。 ・11:39【アフター6ジャンクション】 2018年からTBSラジオで平日よる6時から放送されている番組。最新カルチャーの紹介や分析、注目アーティストのスタジオライブなどの企画を盛り込んだ「文化的情報娯楽番組」。略称である「アトロク」は、いとうせいこうの提案によるもの。 ・13:40【タモリのオールナイトニッポン】 1976年から1983年までニッポン放送で放送されていた、タモリがパーソナリティのラジオ番組。いとうせいこうは早稲田大学在学中にADを務めていた。 ・16:11【極楽TV】 景山民夫によるテレビ番組をテーマにしたエッセイ集。

Hol dir die App, um deine Podcasts mitzunehmen









